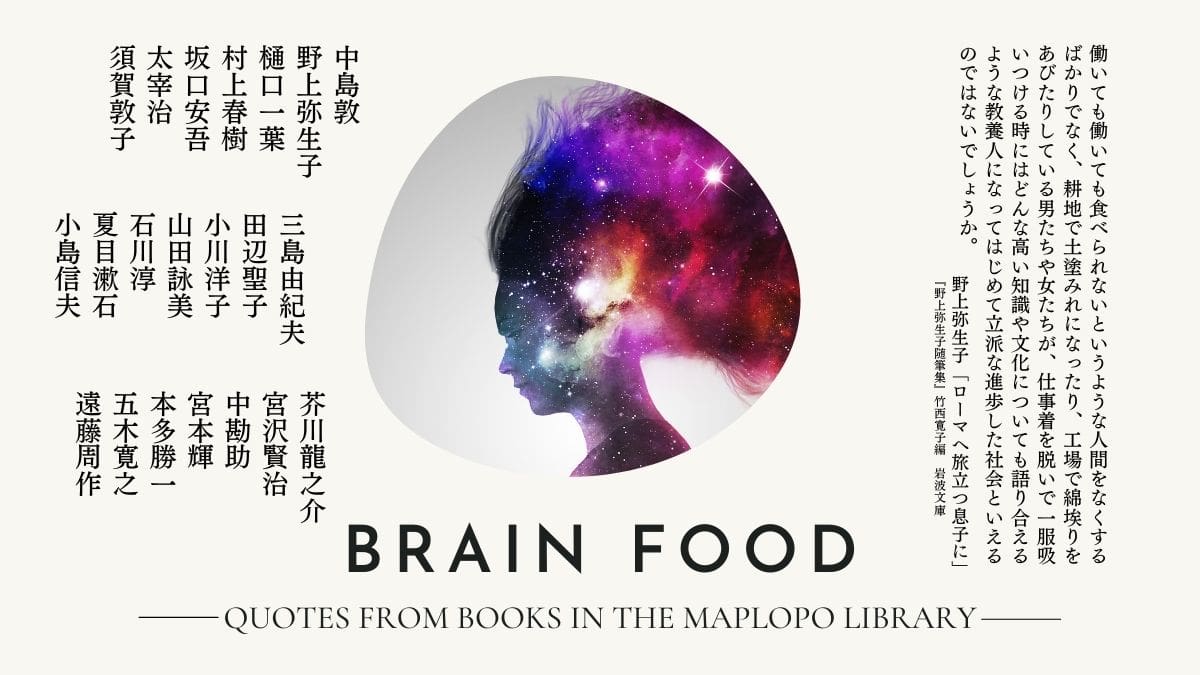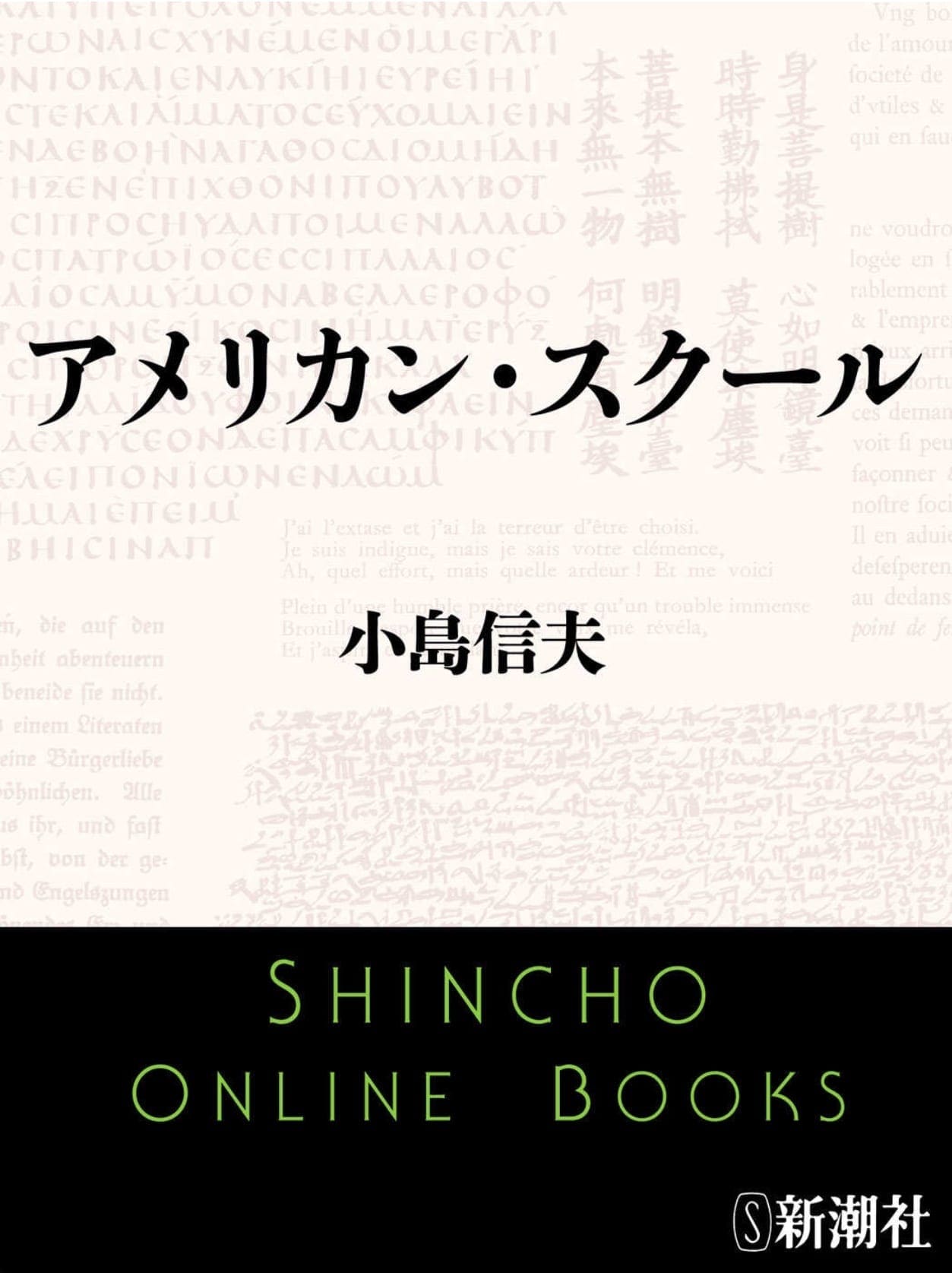
久しぶりの大ヒットだ。小島信夫の「アメリカン・スクール」(1954年発表)がずば抜けておもしろい…… この作品を読んだ後、ずっとそれが頭から離れなくて延々と作者やストーリーのことを考えている。
きっかけは、村上春樹著『若い読者のための短編小説案内』を読んだことから。その中で小島信夫の「馬」についての評論がおもしろかった。村上春樹に「世の中には変な話を書く作家はほかにもたくさんいますが、こういう奇妙きてれつな『変さ』を自然にすらすらと書ける人は、小島さん意外にちょっと見あたらないような気がします……」と言わしめる、不思議であぶない作家・小島信夫。そんな彼に他の「第三の新人」と呼ばれる小説家たち——吉行淳之介、安岡章太郎、庄野潤三などよりも、ずっと魅力を感じた。
なんやろ、彼の独特のおかしさが半端ない。新潮文庫の『アメリカン・スクール』に収録されている「汽車の中」なんかは吹き出し笑いが止まらんほどで、独特すぎる。
「アメリカン・スクール」は最初のほう状況を飲み込むのに時間がかかって、山田やら柴元やら伊佐やら固有名詞が次々でてくるので、誰が誰や?と一回一回確認しながら読まなくてはならず先を読み進めていく気持ちをくじかれそうになる危険もあるが、徐々に物語が勢いづいてきて小島ワールドにどんどん引き込まれていく……
「アメリカン・スクール」の魅力のひとつは、キャラクターの立ち具合であると思う。たとえば山田。彼は英語が大好きで自信満々の教師なのだが、彼の徹底したあくの強さがとことん描かれている。そしてそれに対する主人公の伊佐。彼は同じ英語教師であるのに、英語を話すことに極度の恐怖心を抱いていて、英会話を避けるために、ここまでか!というぐらいあの手この手であらゆる策を講じる。そして女教員のミチ子。彼女が、彼女をナメてかかってる自信満々の山田に切り返す文句「あなたの英語のどの発音がアメリカ南部で、どの発音が東部で、日本で云えば、青森弁に九州弁がまざっているようなものですわ」にはふふっとなった。
好きな場面・おもしろい所はあまりにも多すぎて全部を全部紹介しきれないのだが、特にいいと思うところを引用しながら挙げていくことにする。
まずは教師の一行が県庁から6キロ先のアメリカン・スクールまで徒歩で移動しているところで、このくだりが好き。
……山田は鷹のように最後尾の伊佐をねらっていた。彼の位置からふりかえってみると山田の憤るのもむりはない。その一行は、じっと山田が佇んでいる横を三々五々通って行くが何のために歩いているのか、米兵でなくとも聞いてみたくなるような、ダレた歩きぶりであった。彼は伊佐の近づくまで待っていようと思った。彼は先日来、伊佐が自分に何ごとか反抗心をいだいているのを気にしないわけには行かない。彼は 「規律破壊者」という言葉を佇みながら考えだした。そうすると伊佐という男はすべて解釈がつくように思われた。
(中略)
伊佐より前にミチ子が山田のそばを通った。
「靴ずれなんですよ、あの人」
「靴ずれ?そんなバカな」
山田はただの 「規律破壊者」ではなくて、靴ずれであると聞いて、ただの 「規律破壊者」以上に規律破壊者だと思った。そのような幼稚な理由でおくれていることは許せない。そんなふうだとこの男はそのうち便所に行きたいだの、喉が痛いだのといっておくれるかも知れない。第一、その靴は何だ。山田は伊佐の黒い靴がアスファルトの地面をするように歩いてくるのをじっと見ていた。その白く埃をかぶった黒靴が山田をおそれるかの如く彼の前に寄ってきた時、山田ははじめて声をかけた。
「それはキミの靴ですか (英語 )」
山田という教師は、怒りがこみあげてくるとますます英語が出てきて、日本人に対してもバンバン英語を使う。ちょっと英語が得意な人がいるとその実力を試してやろうと、武道家が腕比べに相手に戦いを挑むように、遮二無二話しかけていく。「オー、シェイムフル(恥ずかしい)」が口癖で、作中たびたび出てくる。私は文学作品中に、英語で話されたことを示すのに括弧書きで(英語)とつけられてるのを今まで見たことがなく、それがここで普通に出現していて、ちょっと以外で思わず吹き出してしまった。
また、靴ずれで負傷している伊佐をジープに乗せてあげようと寄ってくる米兵から逃れようと、伊佐が畑に飛び込んで、いいんですいいんです自分のことは放っておいてください、と言わんばかりに必死に手を振って拒絶している中、こんな親切を受け取らないとは恩知らずな!と怒り心頭にやって来た山田に捕まえられ、その米兵と二人でジープに放り込まれるところも笑える。
…… 彼だけを乗せたジ ープが、砂塵を残してアッという間に小さくなると、あとで爆笑がおこった。
烏が高いところにいるくせに、群をなしてジ ープをよけるようにそれていた。
カラスまで、不穏な空気を察して避けているのだ。
そして極めつけは、伊佐とアメリカ婦人教師エミリーとのやりとり。英語や英語を話す人種に極端に消極的になっている伊佐は、映画スターのような美しさのエミリーに足のすくむような感じになり、彼女の善意に「サンキュウ」と言いたいけれど言ったらそのあと会話をしていかなくてはならないことに恐怖し、ぶきっちょにおじぎしたり、ただ頷いたりするだけ。
……婦人は何かを語りかけ、いく度も彼に微笑をあたえるごとに伊佐はますます自分が耳がわるくて聞えないふりをした。
(中略)
心の動揺のために、彼はいきなり彼女の持っている分厚い本を持ってやろうと思い立ち、走りよってそれを自分の手にとろうとした。その場合にどのように云えばいいか彼も知らぬわけではなかったが、それを言葉にあらわすのが恥しくて、彼はだまってそうしたのだ。伊佐がむりに奪おうとするので、彼女はグッと本をひいたが、頭をさげ、泣きそうな微笑をうかべながら、しつこく本に食いさがってくるので、はじめて彼女は伊佐の意を察して礼をいったが、彼に渡しはしなかった。しかし伊佐は自分の意が通じたことがわかったので、これから自分がこの学校でどんな能足らずと思われても、少くとも人でなしではないと知ってもらえるだろう、と死に行く者が、生きている者に懺悔をしたときのようなかすかな満足をおぼえたのだ。
この後伊佐は、エミリーの個室から脱出を試みようと窓から抜け出すのだが、裸足で運動場を走っている最中に友人に借りた靴を置き忘れてきたのを思い出して引き返してくる。再び窓から飛び込もうとしたところ、残念無念エミリーに見つかってしまう。この一連部の、テンポのいいドタバタ・コメディー的文章には、クククっとなること必至でございます。
私にとっての小島信夫の魅力は、いちいちおもしろいところにある。わーそんな細かいとこも描写する!みたいな、執拗と言っていいほどの一瞬々々への執着が、非常に滑稽だ。一から八で成り立つこの短編物語にはそんな箇所がたくさんあって、二回目、三回目…と読むときに経験する、貴重なものを新たに掘り当てていく感じが楽しい。何度でも読みに戻ってきてしまうタイプの作品である。
そのほか印象に残ったところ、突いてくるとこ鋭いなぁ…と感心した文をいくつか。
……彼はなおも眼を閉じたまま坐りこんでしまったが、その快さは、小川の囁きのような清潔な美しい言葉の流れであることがわかってきた。それは彼がよくその意味を聞きとることが出来ないためでもあるが、何かこの世のものとも思われなかった。目をあけると、十二、三になる数人の女生徒が、十五、六米はなれたところで、立ち話をしているのだった。
(中略)
彼はこのような美しい声の流れである話というものを、なぜおそれ、忌みきらってきたのかと思った。しかしこう思うとたんに、彼の中でささやくものがあった。
(日本人が外人みたいに英語を話すなんて、バカな。外人みたいに話せば外人になってしまう。そんな恥しいことが……)
彼は山田が会話をする時の身ぶりを思い出していたのだ。 (完全な外人の調子で話すのは恥だ。不完全な調子で話すのも恥だ)
(中略)
(おれが別のにんげんになってしまう。おれはそれだけはいやだ!)
伊佐が英語という言語に対して上位の地位を与えていることが分かる部分。「清潔な美しい言葉の流れ」でこの世のものとは思われないと認めているのに、こんなに英語を忌み嫌っているのはなぜなのか。とても印象的な文。
そしてこれ。
ミチ子は英語で 「彼 」というと何か伊佐の蔭口を云ってもそれほど苦にならないことを知って、伊佐のあれほど英語を話すのを嫌う気持もわかるような気がした。たしかに英語を話す時には何かもう自分ではなくなる。そして外国語で話した喜びと昂奮が支配してしまう。
自分のことを考えてみても、英語を使うときの私と日本語を使うときの私は、実際にやっぱり多少違う。たぶんそれは言語には言語自体に、本来備わっている個性があって、それが自ずと使う人に影響を与えているからだろう。そしてそういうのを経験して実感している人はたくさんいると思う。
この物語では、日本に生まれ育った私が10~20代の頃感じていた、漠然とした外国に対する憧れが思い出された。英語に対する憧れや、英語をかっこよく操る人への憧れ。日本社会をふわーっと取り巻いている英語文化を崇拝する風潮。それはきっと日本が戦争に負けたということと深くつながっていて、そういうのを経験した人たちの気持ちが蓄積されているのだろうと「アメリカン・スクール」を読んだ後思った。
♦
小島信夫年譜
参考文献:村上春樹著『若い読者のための短編小説案内』文春文庫, 2015, 付録 読書の手引き
1915
大正4年2月、岐阜県加納町に生まれる。父の捨次郎は仏壇師。
1932
昭和7年、岐阜県立岐阜中学校を卒業。子どもの頃からの吃音を治療するため大阪桃山の矯正学院に通院する。そのため中学校の卒業式は欠席。
1935
昭和10年、第一高等学校文科甲類に入学。一高では、福永武彦、中村真一郎、加藤周一らとともに文芸部委員となる。
1938
昭和13年、東京帝国大学文学部英文科に入学。同時期に結婚する。矢内原伊作、加藤周一らと、同人雑誌「崖」を発刊。
1941
昭和16年、東大英文科卒業。卒業後、私立日本中学の英語教師になる。
1942-1945
昭和17年、召集により岐阜の中部第四部隊へ入隊。中国に駐屯中、暗号兵としての訓練を受ける。その後中国各地で暗号兵として勤務。昭和19年からは、北京の燕京大学内にある情報部隊に転属。戦後から復員までは部隊の渉外事務に従事する。
1946
昭和21年3月、日本に帰国。岐阜県庁に勤務。昭和23年には上京し、千葉県佐原女学校や東京都立小石川高校で英語教師を勤める。
1952
昭和27年、「小銃」が文芸雑誌・新潮に掲載される。第28回芥川賞の候補となるが落選。
1953
昭和28年、「吃音学院」が第30回芥川賞の候補となるが落選。
1954
昭和29年、明治大学工学部の教師となる。「星」と「殉教」が第31回芥川賞の候補となるが再び受賞を逃す。
1955
昭和30年、「アメリカン・スクール」で第32回芥川賞を受賞する。
1965
昭和40年、「抱擁家族」で第1回谷崎潤一郎賞を受賞する。
1982
昭和57年、「別れる理由」で第35回野間文芸賞を受賞する。
1998
平成10年、「うるわしき日々」で第49回読売文学賞を受賞する。
2006
平成18年10月26日、肺炎により永眠。
Dazai Osamu
Coming soon
Nakajima Atsushi
(中島敦)
LIVE!
Natsume Soseki
Coming soon
Sakaguchi Ango
LIVE!
Nogami Yaeko
(野上弥生子)
Coming soon